こんにちは、岡山矯正歯科の院長 田川 淳平です。
「歯並びが気になる」「笑ったときの口元がコンプレックス」「子どもの将来のために今のうちに矯正治療を始めてあげたい」と思ったとき、多くの方がまず最初に気になるのが、**“矯正治療を始めるにはどんな準備が必要か?”**という点ではないでしょうか。
とくに、「矯正の診断って具体的に何をするの?」「時間はどれくらいかかる?」「診断料って高いの?」「診断だけ受けてもいいの?」といった疑問や不安の声は非常に多く聞かれます。
初めて矯正治療を受ける方にとって、“診断”という言葉は少し専門的で、何をされるのかイメージしづらいものです。
ですが、この**「診断」こそが、矯正治療において最も大切なステップの一つ**なのです。
矯正治療は、美容目的の治療のように見えることもありますが、実際にはれっきとした医療行為であり、ただ見た目を整えるだけでなく、噛み合わせ、将来的な歯の健康などにも深く関わっています。
そのため、安易に始めるのではなく、事前に精密な診断を行って、患者さん一人ひとりに合った治療方針を立てることが非常に重要です。
この記事では、「矯正治療の診断では何をするのか?」「診断の流れはどうなっているのか?」「診断から装着までの期間はどのくらいかかるのか?」「診断料や検査費用はいくらぐらいかかるのか?」といったポイントを、矯正専門クリニックの視点からわかりやすく、丁寧に解説していきます。
「矯正治療を考えているけれど、最初の一歩がなかなか踏み出せない」という方が、不安を解消して安心して治療に進めるよう、具体的な診断内容や費用、必要な時間、装置をつけるまでのステップなどをしっかりご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
- 矯正治療における「診断」とは?
- 診断前に行う検査の内容とは?
- 模型(石膏模型)はなぜ作る?その役割と工程
- 診断結果が出るまでの流れと所要時間
- 診断料や関連費用の目安と内訳
- 診断結果から治療方針が決まるまで
- 診断から装置装着までのスケジュール
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:診断は矯正治療の土台となる大切なプロセス

1. 矯正治療における「診断」とは?
矯正治療における「診断」とは、患者さんの口腔内や顔貌、骨格などの状態を総合的に評価し、その方にとって最適な治療法を決定するための精密なプロセスです。
「歯並びが悪いから、ただ装置をつけて動かせば良い」という単純なものではありません。噛み合わせのバランス、顎骨の大きさや形態、顔全体の印象や将来的な安定性など、さまざまな情報を医学的に分析した上で治療計画が立てられるのです。
たとえば、以下のような項目を診断で詳しくチェックします:
- 歯の位置や傾き、重なりの程度
- 上下の前歯のズレ 前後(反対咬合)・左右(交叉咬合)・上下(開咬・過蓋咬合)
- 上下の奥歯のズレ
- 顎の骨の大きさやバランス、左右差
- 舌や唇、頬の筋肉の動きや癖
- お子さんであれば、骨の成長段階
診断の結果によっては、「抜歯が必要かどうか」「マウスピース矯正が適しているか、それともワイヤー矯正が効果的か」「治療にかかる期間はどの程度か」「費用はどのくらいかかるか」「いつから装置をつけられるか」といった、矯正治療に関わるすべての要素が決まっていきます。
また、診断によって初めて**「この患者さんにとって本当に治療が必要かどうか」**も判断できます。
逆に、一見歯並びが悪くなさそうでも、噛み合わせに大きな問題が隠れている場合もあります。
このように、診断は矯正治療の“出発点”であり、矯正治療の質と安全性を左右する非常に重要な工程です。
適切な診断が行われなければ、治療方針がずれてしまい、治療が長引いたり、思ったような結果が得られなかったりするリスクも高まります。
診断には時間も費用もかかりますが、それは**「患者さん一人ひとりの状態に合わせて、確実で安全な矯正治療を提供するため」**のものです。
検査内容や所要時間、診断料や料金の内訳などは、次の章で詳しく解説しますので、ぜひ続けてお読みください。
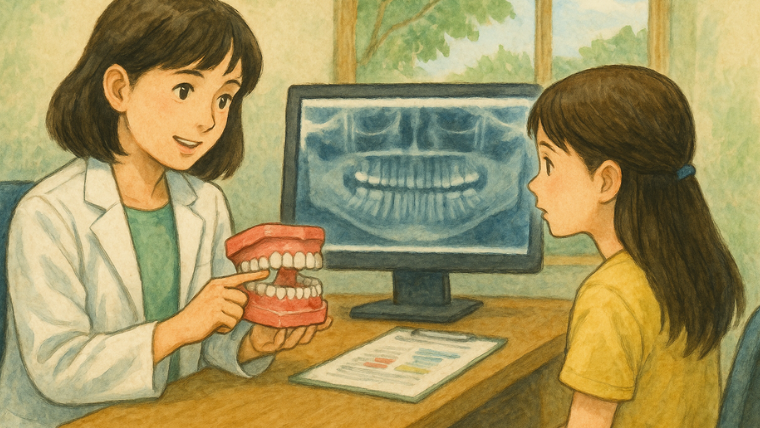
2. 診断前に行う検査の内容とは?
矯正治療の診断では見た目や感覚だけで判断するのではなく、客観的なデータをもとに科学的かつ論理的に分析するために、診断前に検査を多数行います。
それぞれの検査には明確な目的があり、単に“たくさん検査するから安心”というわけではなく、的確な治療計画を立てるために必要不可欠なものです。
以下に、主な検査項目とその目的を詳しく解説します。
① 口腔内写真の撮影(歯の状態を正確に記録)
口腔内写真は、上下の歯の状態、前歯の咬み合わせ、奥歯の咬み合わせ、歯列全体の並び方などを複数の角度から撮影します。
この写真は診断資料として保存されるほか、治療の経過観察や、治療前後の比較、また患者さん自身への説明にも活用されます。
目に見えない微細な歯の傾きや、ブラケットの装着位置を決める際にも参考にされます。
② 顔貌写真の撮影(横顔・正面からのバランスを分析)
正面・側面・斜めからの顔の写真を撮ることで、口元の突出感や左右非対称、Eラインとのバランス、顎の位置、笑った時の歯茎の見える量などを評価します。
とくに成人の患者さんにとっては、矯正治療のゴールが「見た目の改善」であることも多いため、顔貌写真の分析は審美面でも重要な役割を果たします。
治療前後での印象の変化を比較する材料にもなります。
③ レントゲン撮影(骨や歯根、成長状況の把握)
レントゲンには主に以下の2種類があります。
- パノラマX線(パントモ):すべての歯とその根、顎の骨の状態、親知らずの有無、歯の生え変わりの進行状況などを一度に確認できる画像。
- セファロX線(側貌頭部X線規格写真):顔全体の骨格バランス、上下顎骨の位置関係、成長方向を分析するための専門的な画像。
セファロのデータは、治療方針の立案や、成長予測のシミュレーション、治療の安定性を検証する上で非常に重要な情報源となります。
④ 歯列の印象採得(型取り)または口腔内スキャン
患者さんの歯型を取る工程です。
従来のアルジネート印象材を使う方法に加え、近年では口腔内スキャナーによるデジタル印象を採用するクリニックも増えています。
歯の並び方、1本1本の角度、咬み合わせの位置を正確に記録し、石膏模型や3D模型を作成するための基礎資料となります。
⑤ 咬合・顎関節のチェック(動き・ズレ・異常音)
上下の歯がどのように咬み合っているのか、咬み合わせ時にどこかにズレがあるか、顎を開け閉めしたときにカクッと音がしたり、痛みが出たりしていないかを細かくチェックします。
これにより、顎関節症の有無や、矯正治療に支障をきたすような咬合の異常があるかどうかを判断できます。
⑥ 舌癖・呼吸・口唇の癖などの観察
舌で前歯を押す癖(舌癖)や、無意識のうちに口をポカンと開けている習慣(口呼吸)、唇や頬を噛む癖などは、歯列の状態や顎の成長に影響を及ぼすことがあります。
これらの癖がある場合には、治療と並行して**MFT(口腔筋機能療法)**や生活習慣の指導が必要になることもあります。
このように、矯正治療の診断では非常に多角的な視点から口腔内と顔全体を評価します。
検査項目が多いと感じるかもしれませんが、それぞれに明確な目的と意味があり、精度の高い治療に欠かせないステップです。
3. 模型(石膏模型)はなぜ作る?その役割と工程
矯正治療において欠かせない診断資料のひとつが「模型」です。
これは、患者さんの歯列と咬み合わせを立体的に再現したもので、従来は石膏を使って作られることが多く、「石膏模型」と呼ばれています。
模型の役割とは?
矯正歯科医師はこの模型を使って、患者さんの歯列全体を上から、横から、裏側から観察します。
模型があることで、次のような重要な情報が得られます:
- 歯列のアーチ形状(狭い・広い)
- 歯の傾斜やねじれの状態
- 左右のバランス・非対称の有無
- 咬合関係(奥歯の当たり具合・前歯の咬み合わせ)
- スペースの足りなさ(叢生)や空隙の有無
また、治療前と治療後の模型を比較することで、どれだけ改善したかを一目で確認できる可視的な記録資料にもなります。
模型は治療方針の決定にどう関わる?
たとえば、前歯に重なりがある「叢生(そうせい)」の患者さんの場合、どれくらいのスペースが不足しているかを正確に測定することで、歯列の拡大で対応可能か、抜歯が必要かなどが判断できます。
また、左右の歯の傾きや噛み合わせのズレも、写真やレントゲンでは把握しきれないこともあり、模型を使った咬合診断が極めて重要になります。
石膏模型の作成工程
- 型取り(印象採得)
柔らかいアルジネート素材などを口の中に入れて、歯列の型をとります。苦手な方もいますが、短時間で終了します。 - 石膏流し込み・硬化
採得した型に石膏を流し込み、30分ほどかけて固めます。 - 模型の整形・仕上げ
余分な部分を削り、観察しやすいように形を整えます。
デジタルスキャンによる3D模型の活用
近年では、口腔内スキャナーを使用したデジタル模型の導入が進んでいます。
光学的に歯列のデータを取得し、コンピュータ上で立体的に再現するため、石膏模型よりもスピーディーかつ衛生的に扱えます。
3Dデータはクラウドで管理されるため、治療経過の比較、矯正装置の設計、患者さんへの説明にも活用できるなど、メリットは多くあります。
ただし、歯の接触状態(咬合の正確な当たり)を物理的に確認したい場合は、石膏模型が今でも非常に重要な役割を果たしています。
模型(石膏・3Dいずれも)は、患者さん自身が目で見て理解できる「治療の地図」とも言える存在です。
見た目だけでなく、矯正歯科医師の診断精度にも直結する非常に重要な資料であることを、ぜひ知っておいてください。

4. 診断結果が出るまでの流れと所要時間
矯正治療のための精密検査がすべて終わった後、「いつ診断結果が出るのか?」「その結果はどうやって伝えられるのか?」「その後はどうなるのか?」といった疑問を抱く患者さんは少なくありません。
ここでは、診断から治療方針が決定し、患者さんへ説明されるまでのプロセスを詳しく解説します。
所要時間についても段階ごとに目安をお伝えします。
ステップ①:検査データの集約と整理(1〜2日)
まず、写真撮影・レントゲン・模型・スキャンデータなど、診断に必要な資料をすべて集め、矯正歯科医師が一元的に確認できるように整理します。
口腔内の状態を立体的・多角的に把握するために、資料ごとに異なる角度からの分析が必要です。
この段階で、以下のような資料が揃います:
- セファロX線画像(骨格・上下顎の位置分析)
- パノラマX線画像(歯根・歯の本数・親知らずの有無)
- 顔貌写真(正面・側面・スマイル時など)
- 模型または3Dスキャンデータ(咬合状態・アーチ形状)
- 口腔内写真(歯列全体・前歯・奥歯・上下の接触)
これらは見た目だけで判断するのではなく、レントゲン画像であればトレース(骨格の輪郭線の描出)などを行い、診断ソフトを用いて数値化をして、科学的な根拠を持って評価されます。
ステップ②:検査結果の分析(1〜2日)
すべての資料が揃ったら、矯正専門医が詳細な分析を行います。
内容は以下のように細分化されます:
- 骨格診断(上下顎・顔面のバランス分析)
→ セファロ分析により、上下顎骨の前後・上下の位置関係を評価。 - 歯列の問題点の抽出
→ ガタガタの量(叢生)、出っ歯、開咬、交叉咬合などを確認。 - 咬合診断
→ 奥歯の咬み合わせ、上下の前歯の重なり(オーバーバイト/オーバージェット)を評価。 - 治療可能性・安定性の検討
→ 年齢・骨格・口腔習癖を踏まえ、治療の実現可能性や安定性・後戻りのリスクを判断。 - 抜歯/非抜歯の判断
→ スペースの不足量や歯の傾きから抜歯の必要性を判断。
また、デジタル模型がある場合には、コンピュータ上で歯の動きをシミュレーションする「バーチャルセットアップ」が行われる場合もあります。
これは、治療後の歯並びの完成予想を画像や動画で確認できる非常に有用な手段です。
ステップ③:治療方針の立案(1日〜数日)
分析結果をもとに、矯正歯科医師が患者さんごとの**個別治療計画(Treatment Plan)**を立てます。
ここでは、以下のような内容が決定されます:
- どの装置を使うか(ワイヤー矯正、マウスピース矯正など)
- 抜歯が必要かどうか(抜歯部位とその理由)
- 治療期間の目安(おおよねの年月数)
- 費用の総額(料金プラン、装置料など)
- 装置をつけるタイミングと準備事項
- 治療中の生活指導(楽器演奏、スポーツ、食事制限など)
- 治療後の保定についての見通し
こうした内容は、患者さんの希望やライフスタイルを反映しつつ、医学的根拠にもとづいた合理的な提案としてまとめられます。
ステップ④:診断書(診断結果の説明事項)の作成(1週間前後)
診断から約10日から2週間程度で、**「診断結果説明のための来院」**をお願いするケースが多いです。
この診断では、矯正歯科医師が診断結果をもとにスライドや模型を使いながらわかりやすく解説し、患者さんが納得した上で治療に進むかどうかを決めていただきます。
時間の目安としては30〜60分程度の説明時間を確保することが多く、以下の資料が提示される場合があります:
- 診断結果のまとめ(紙またはPDF)
- 料金表・支払い方法一覧
- 矯正治療同意書・契約書の説明
患者さんが不安を感じず、十分に質問できる環境が整っていることが理想です。
5. 診断料や関連費用の目安と内訳
矯正治療にかかる費用の中でも、「診断料」や「精密検査費用」がどのような内容で構成されているのか、明確に理解できていない方も多いかもしれません。
この章では、診断にかかる費用の項目・相場・医院ごとの違い・支払い方法のパターンなどを詳しく解説します。
診断料とは何にかかる費用?
診断料とは、主に以下のような作業に対して発生する費用です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 精密検査費 | レントゲン撮影、顔貌・口腔写真、印象採得(スキャン含む) |
| 診断費 | 検査結果の分析、治療計画立案、診断結果説明、治療方針の提案、装置の種類などの相談 |
これらは一人ひとりに合わせて手間と時間をかけて行うものであり、画一的なマニュアルでは対応できない“オーダーメイド”の工程といえます。
診断料の相場と料金体系
一般的な矯正歯科クリニックでは、診断料として20,000〜60,000円程度の費用がかかることが多いです。
以下に参考相場を示します。
| 項目 | 費用の目安(円) |
|---|---|
| 精密検査・診断一式 | 50,000〜150,000程度(医院により異なる) |
| 初診相談(カウンセリング) | 無料〜10,000程度(医院により異なる) |
診断料の支払い方法とタイミング
支払い方法は以下のようなパターンがあります:
- 現金支払い(診断当日)
- クレジットカード対応(医院による)
- 銀行振込(後日精算)
6. 診断結果から治療方針が決まるまで
矯正治療における「診断」は、単なるお話ではありません。
その診断結果に基づいて、どのような治療をどの順番で、どれくらいの期間をかけて行うのかという、全体の治療方針が決まる非常に重要なステップです。
診断結果をもとに、矯正専門医が患者さん一人ひとりに合わせた**個別の治療計画(Treatment Plan)**を作成し、その内容が患者さんに丁寧に説明されます。
ここでは、治療方針がどのように決まるのか、どんな点が検討されるのかを詳しく解説します。
治療方針を決定するうえでの主な検討項目
矯正治療の方針は、以下のような複数の観点から総合的に判断されます。
① 現在の歯並び・咬み合わせの問題点
- 歯の重なり(叢生)や出っ歯(上顎前突)
- すきっ歯(空隙歯列)や開咬、交叉咬合
- 顎のズレや左右非対称、咬合の安定性
② 骨格や顔貌バランスの評価
- 横顔(Eライン)、顎の突出感
- 上下顎の位置関係(骨格性の要因)
- 将来的な成長予測(特に成長期のお子さん)
③ 治療装置の種類の選択
- 表側ワイヤー矯正、裏側矯正、マウスピース矯正(インビザライン等)など
- 見た目、痛み、装着感、発音、取り外しの可否などの希望を加味
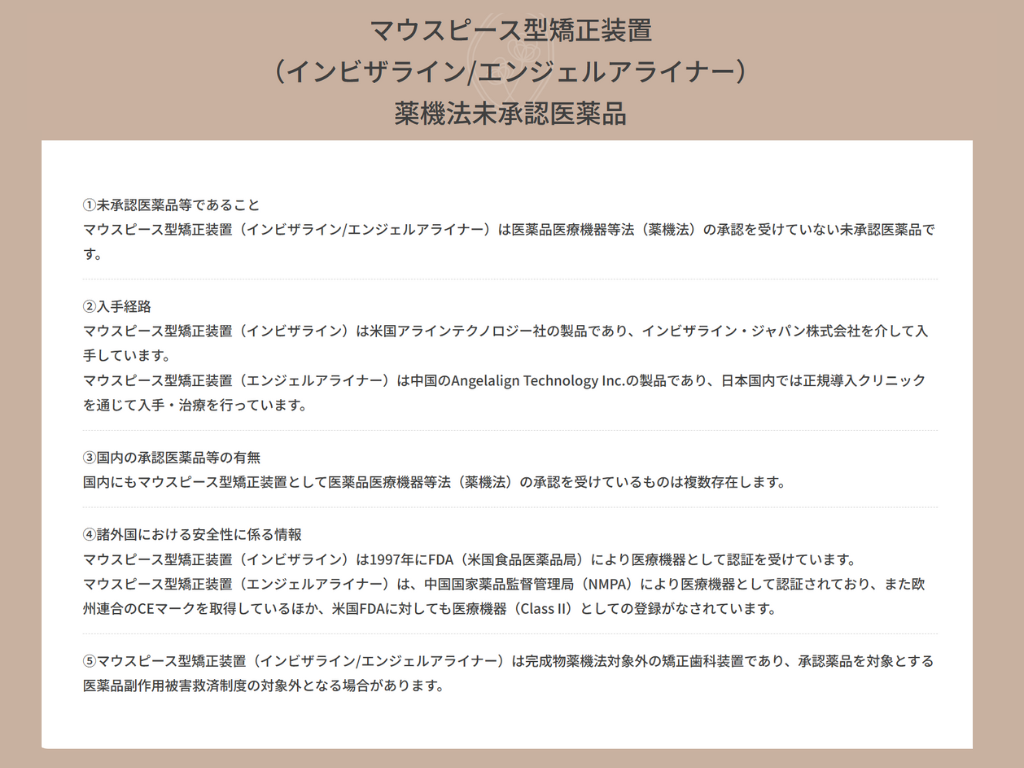
④ 抜歯の必要性とその範囲
- 歯を並べるスペースが不足している場合
- 顔貌バランスを整えるために必要な場合
- 非抜歯でも可能かを検討(IPRや拡大で対応できるか)
⑤ 治療期間の目安
- 症例の難易度、装置の種類、患者さんの年齢や協力度によっても変動
- 一般的には1〜3年が多いが、部分矯正など短期間の症例も
⑥ 費用と支払い方法
- 総額の費用、内訳、調整料の有無、保定装置の費用
- 分割払い(デンタルローン)やクレジットカード支払いの対応可否
⑦ 治療中・治療後の生活への影響
- 食事制限、口内炎のリスク、楽器演奏やスポーツ活動への影響
- 治療後の後戻りを防ぐ保定装置の使用期間や注意点
診断のカウンセリングで大切なポイント
治療方針の説明は、医院によっては**「診断説明カウンセリング」**という形で1時間ほどかけて行われることが多く、以下のような内容を丁寧に確認します:
- どのような状態で、どんな治療が必要か
- 抜歯が必要かどうか、その理由
- 使用する装置とそのメリット・デメリット
- 治療期間の見通し(開始から装置除去まで)
- 費用の総額と支払い方法
- 治療のステップや来院頻度の目安
- 保定装置(リテーナー)まで含めた全体の流れ
患者さんが十分に納得した上で治療に進めるよう、質問の時間をたっぷりと確保している矯正歯科医院が多く、「矯正治療は一度始めたら戻れない」という不安を軽減するための工夫がなされています。
セカンドオピニオンも選択肢の一つ
診断結果を聞いて、「本当に抜歯が必要なのか?」「マウスピース矯正はできないのか?」といった不安がある場合は、他の矯正専門医によるセカンドオピニオンを受けるのも良い方法です。
矯正歯科医師の考え方や治療方針には多少の差があるため、複数の意見を比較することで、より納得して治療を始められることもあります。
7. 診断から装置装着までのスケジュール
矯正治療を検討している方にとって、「診断後、実際に矯正装置をつけるまでにどのくらいの時間がかかるのか?」というのは非常に気になるポイントです。
この章では、診断後に装置をつけるまでの流れと、それぞれのステップにかかる時間の目安を詳しくご紹介します。
一般的なスケジュール例
多くの矯正歯科医院では以下のような流れで進みます(初診から装置装着まで):
- 初診カウンセリング(無料〜3,000円程度)
→ 所要時間:約30分〜1時間
→ 治療の希望を伺い、矯正の必要性を大まかに判断 - 精密検査・診断の予約
→ 日程を決めて後日実施(繁忙期は数週間後になることも) - 精密検査の実施(検査料20,000〜60,000円前後)
→ 所要時間:約1〜1.5時間
→ レントゲン、口腔内写真、模型(またはスキャン)などを実施 - 診断結果の分析と治療計画の作成
→ 約10日~2週間(医院により即日対応のところもあり) - 診断結果の説明と治療方針の決定(診断料30,000〜100,000円前後)
→ 所要時間:約30分〜1時間
→ 装置の種類、治療期間、料金などを説明し、契約の可否を決定 - 契約・装置作製の準備
→ 契約書の記入、支払い方法の確認、装置のオーダー
→ 装置の種類によっては3Dスキャンデータをもとに歯科技工所で製作
→ 製作期間は約3〜5週間 - 矯正装置の装着
→ 表側ワイヤー装着は最短で即日
→ マウスピース矯正は装置が届き次第、最初のマウスピースをお渡し
装置装着までにかかるトータルの時間
| ステップ | 期間目安 |
|---|---|
| 初診から診断まで | 約2〜3週間 |
| 装置作製(装着準備) | 約1〜4週間 |
| 合計 | 約3〜7週間程度 |
※ただし、患者さんの都合や医院の混雑状況により前後する場合があります。
マウスピース矯正の場合のスケジュール上の特徴
インビザラインなどのマウスピース矯正は、装置を海外で製作するため、診断から装着までの期間が長くなる傾向があります。
- 精密検査 → 3Dスキャンデータ送信 → 治療計画の作成 → 製作 → 納品
- この流れだけで3〜6週間かかることもあります。
そのため、早めのスタートを希望される方は、診断日を早めに確保しておくことがポイントになります。
矯正装置装着までにやっておくべきこと
診断が終わってから装置を装着するまでの期間は、比較的自由時間があるため、以下のような準備をしておくとスムーズです:
- ホワイトニングやクリーニング(希望があれば)
- 食事や歯磨き習慣の見直し
- 治療中の食生活や仕事・学校スケジュールの確認
装置装着前の準備期間をうまく活用することで、より安心・安全に治療をスタートすることが可能になります。
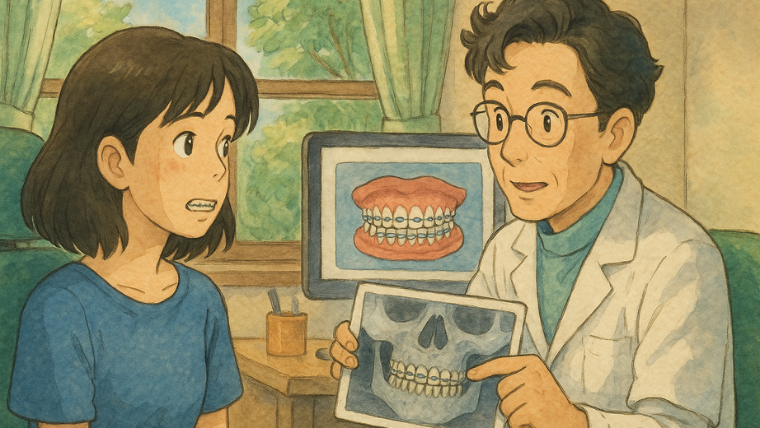
8. よくある質問(FAQ)
矯正治療の「診断」は、普段なじみのないプロセスだからこそ、たくさんの疑問や不安が生まれやすいステップです。
この章では、実際に患者さんからよく寄せられるご質問を厳選し、具体的かつ丁寧にお答えします。
Q1. 診断だけ受けて、矯正治療を始めるかどうかは後で決めてもいいですか?
A. はい、可能です。
診断を受けたからといって、必ず矯正治療を開始しなければならないというわけではありません。むしろ、治療の必要性や方向性をきちんと理解するために診断だけを受けるというのは、非常に合理的な選択です。
診断の結果を見てから、「今すぐ始めるべきか」「将来のために計画だけ立てておくか」「別の装置を検討するか」などを、じっくり考える時間を持つことも大切です。
なお、矯正歯科医院によっては診断結果の有効期限を設けている場合もあるため、数ヶ月以上あける場合は再検査が必要になることもあります。
Q2. 子どもにも診断が必要ですか?いつ受けさせるのがベストですか?
A. お子さまの場合でも、診断はとても重要です。
とくに6〜10歳の混合歯列期(乳歯と永久歯が混在している時期)は、歯並びだけでなく骨格の成長や癖などもチェックすることが治療の鍵となります。
「まだ小さいから矯正は早いのでは?」と感じるかもしれませんが、実際には、早期に診断しておくことで、成長の力を利用した負担の少ない治療が可能になるケースもあります。
診断では、永久歯の萌出状況、顎の骨の成長方向、口呼吸や舌癖などのチェックも行います。矯正の必要性がなかったとしても、「安心材料」として非常に有意義です。
Q3. 診断から矯正装置装着まで、最短でどのくらいの日数がかかりますか?
A. 最短で2〜3週間程度、通常は1か月前後が目安です。
矯正歯科医院の混雑状況や、マウスピース矯正の場合の製作期間によっても変動しますが、スムーズにいけば初診から診断(診断結果説明、契約)を経て装置の準備までを3〜7週間で完了できるケースもあります。
ただし、虫歯治療や歯のクリーニング、口腔習癖の改善が必要な場合には、もう少し時間がかかることもあります。
早めに矯正治療を開始したい方は、初診相談時に「最短でいつから始められますか?」と尋ねると良いでしょう。
Q4. 検査時に気をつけるべき服装や持ち物はありますか?
A. 顔や口元がよく見えるような服装を心がけましょう。
顔貌写真や口腔内写真を撮影する際、ハイネックやマフラー、帽子、濃いメイク、大きなピアスなどは避けた方がスムーズです。
9. まとめ:診断は矯正治療の土台となる大切なプロセス
矯正治療を検討する際、多くの方が「どんな装置をつけるのか?」「どれくらいの期間がかかるのか?」「費用は?」といった“治療の本番”に注目しがちです。
そのすべてのスタート地点となるのが、「診断」というプロセスです。
この「診断」こそが、安全で的確な矯正治療を実現するための土台であり、その後の治療結果を大きく左右する極めて重要なステップであることを、この記事を通してご理解いただけたのではないでしょうか。
矯正治療の診断がもたらすメリット
- 自分の歯並びや骨格の状態が客観的にわかる
- 抜歯の必要性や装置の選択が医学的根拠をもとに説明される
- 治療のゴールと期間、費用の全体像が明確になる
- 納得した上で治療をスタートできる
- 不安な点を事前にすべて質問できる
「診断から装着まで」は、信頼関係の第一歩
診断とは、患者さんと矯正医が「これから一緒に治療を進めていくための信頼関係を築く第一歩」でもあります。
丁寧に話を聞いてもらえる、きちんと説明してもらえる、その安心感がそのまま治療の継続意欲や通院のしやすさにも直結します。
診断は受けた時点で“知識という資産”になる
仮に今すぐ矯正治療を始めないとしても、診断を受けることで得られる情報は、将来の治療選択や健康維持において非常に大きな財産となります。
自分の歯並びの傾向や噛み合わせの問題点、骨格バランス、成長予測などを知っておくことで、「治療するならいつがベストか?」という判断材料になりますし、お子さまの成長に合わせた対応も取りやすくなります。
不安があるなら、まずは一歩。診断から始めましょう
「装置が目立ちそうで不安」「治療費が高そう」「痛みが心配」──そんな不安を抱えている方こそ、まずは診断だけでも受けてみてください。
診断は、治療を無理にすすめるものではなく、あなたにとって最善の選択肢を一緒に探すための大切な時間です。
最後に:
この記事が、矯正治療を考えている方の「第一歩」を後押しできたなら幸いです。納得のいく治療のために、まずは“知る”ことから始めてみませんか?
当院では、一人ひとりの患者さんに最適な矯正治療を提案し、治療中も患者さんが相談しやすい快適な環境を作るよう心掛けています。
矯正治療に興味のある方はお気軽にご相談ください。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
この記事を読んだ方が、より良い矯正治療を受けられることを願っています。
今後もどうぞご贔屓ご鞭撻のほどを。





